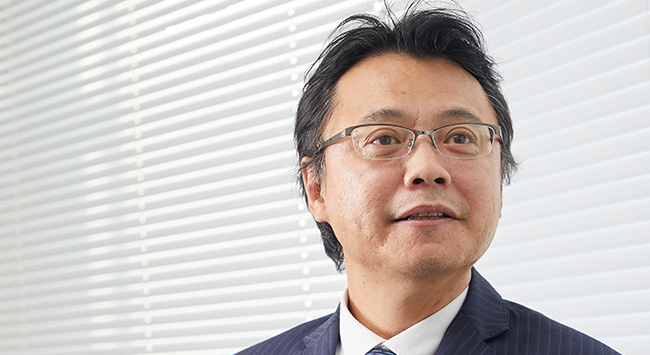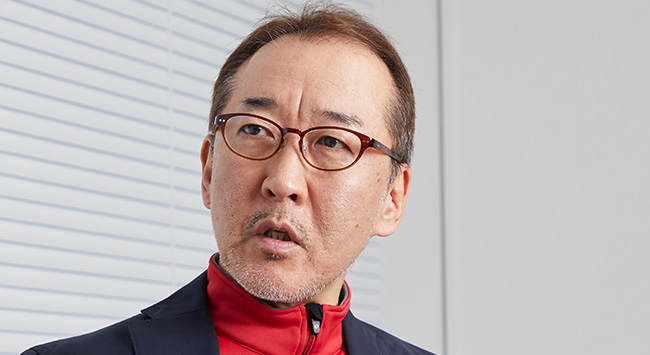未来を拓くひら。大志を! Vol.2
サイエンス作家・竹内薫さんが「触媒一筋」鈴木賢さんに聞いた
制約は修行。
若いうちはがむしゃらに
「自分の目」「化学の目」持ち、独創技術で次代を築け

- 「触媒一筋」鈴木 賢さん
- サイエンス作家 竹内 薫さん
旭化成が掲げる「Care For People, Care For Earth」を具現化するための、製品、技術、同社の研究者たちの取り組みや思いを、サイエンス作家・竹内薫さんをナビゲーターに紹介するシリーズ。第2回は「触媒一筋」の鈴木賢さんに聞いた。触媒は化学プロセスの心臓部ともいわれ、その力量が事業展開の成否を分ける。触媒の魅力、研究者としての転機、鈴木さんが考えるイノベーションに必要な環境とは。
「金ナノ粒子」を使い開発。
プラスチックの原料を
効率生産する触媒
物理が専門で化学が苦手だったこともあり、それ自体は変わらない触媒というものが、昔から不思議でした。
触媒は、化学反応においてそれ自身は変化せず、その存在が他の物質の反応速度を速めたり、目的とする反応を選択的に促進させたりする働きをします。
しかも理論上は量も減らない。やはり不思議ですね。鈴木さんが開発した触媒で作るメタクリル酸メチル(MMA)はアクリル樹脂や塗料の原料です。具体的には何に使われていますか。
その優れた透明性と抜群の耐候性を生かして、ディスプレーや自動車部品、照明・建築関連材料、そして光学材料などに使われています。例えば水族館の水槽は分厚いガラスに見えますが、実はアクリル樹脂なんです。「プラスチックの女王」と呼ばれるくらい美しく、世界的にも需要があります。
その合成方法が「メタクロレインの酸化エステル化法」、通称「直メタ法」ですね。
そうです。世界ではさまざまな製法からMMAが生産されていますが、我々の方法は高効率、低コストを実現した独自のプロセスです。2008年に金のナノ粒子を使った「コアシェル型金・酸化ニッケルナノ粒子触媒」の実用化に成功しました。金と聞くと、コストがかかると思われるかもしれません。でもこの触媒は、少ない金の使用量で高い活性が得られ、しかも長寿命・省資源化と高い経済性を実現しました。触媒は、いわば化学プロセスの心臓部、その力量が事業展開の成否を分けるのです。
 容器に入っているモノが「金-酸化ニッケル触媒」。容器はアクリル樹脂製で、この触媒反応を活用して作られている
容器に入っているモノが「金-酸化ニッケル触媒」。容器はアクリル樹脂製で、この触媒反応を活用して作られている
CO2の資源化も目指す、
グリーンケミストリー
夢というのは、例えば二酸化炭素(CO2)や環境に関連する研究でしょうか。
そうですね。持続可能な社会の実現に向けた環境・エネルギー分野の研究開発に力を注いでいます。細孔構造が精密に制御された特殊なゼオライトを用い、発電所や工場の排ガスからCO2を効率よく分離・回収するシステムの開発を進めています。また、CO2の転換技術では、ポリカーボネート(PC)原料やウレタン樹脂原料も事業化の段階にあるほか、機能性化学品を合成する新技術も開発中です。CO2が安価に回収できて再エネが普及する今後は、燃料や汎用化学品に転換する技術も重要になってくると考えています。
そうなってくるとCO2の削減に大きく貢献できますね。
弊社はもともと、CO2を原料にしたPCの製造技術を世界に先駆けて実用化しています。そういう歴史もあり、グリーンケミストリーの研究では世界のトップランナーだという自負があります。
最近読んだ本で、6度目の地球の絶滅期の到来を危惧するものがありました。過去5回の大量絶滅期のうち、4回は地球温暖化が関係しているらしいです。CO2対策は必須ですが、何か製品に取り込んでしまえれば結果的に減らせるわけですね。