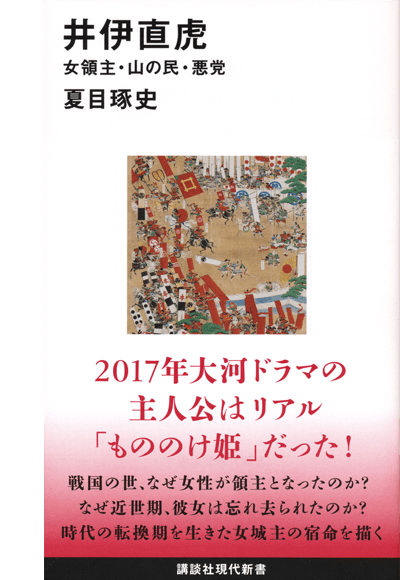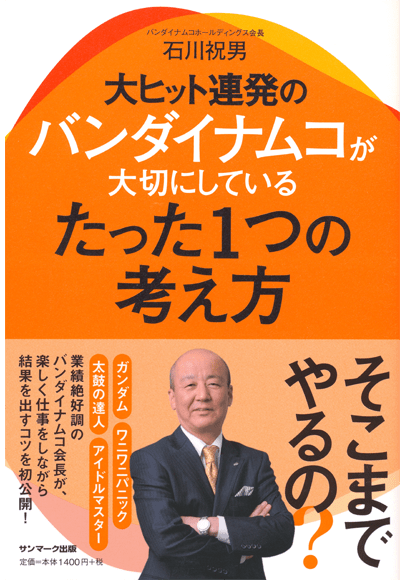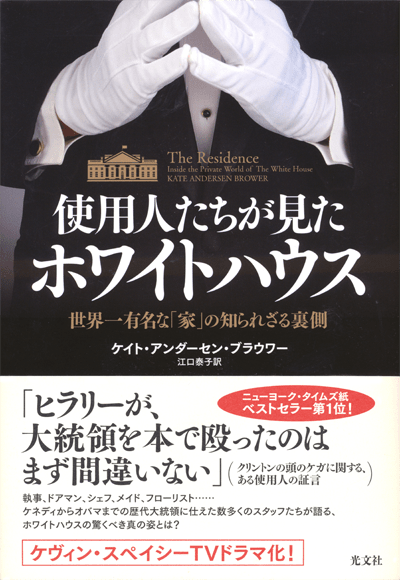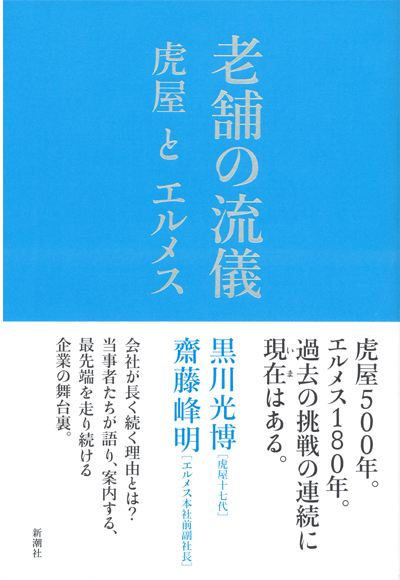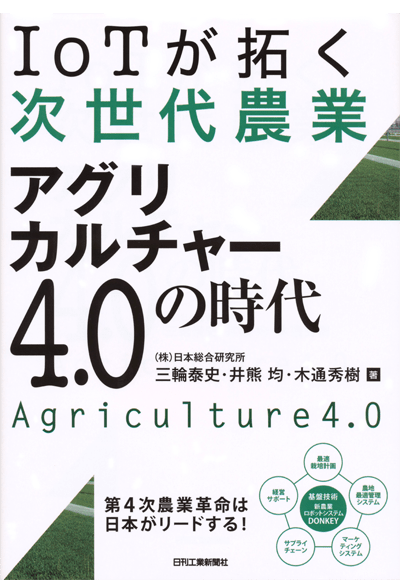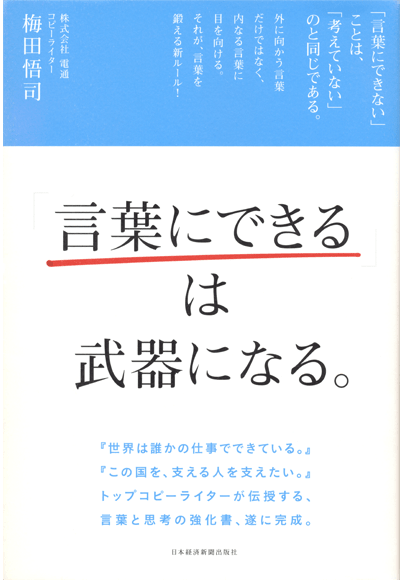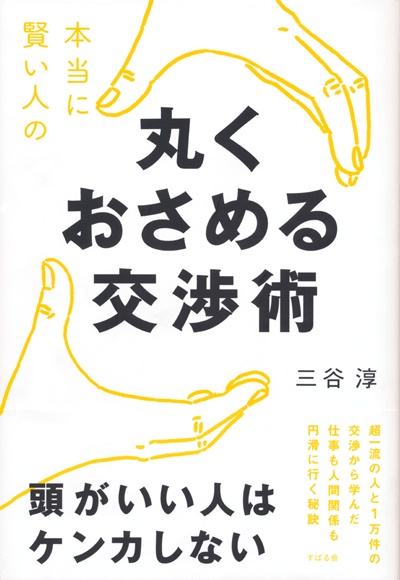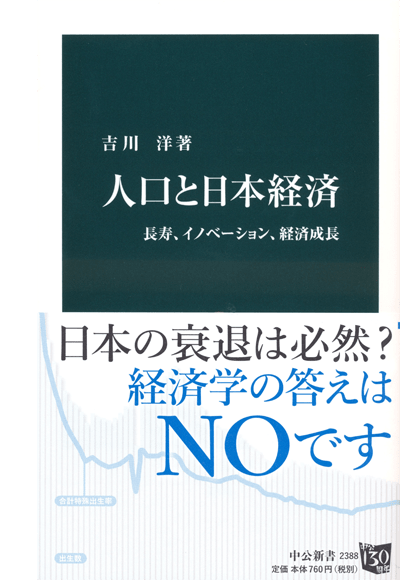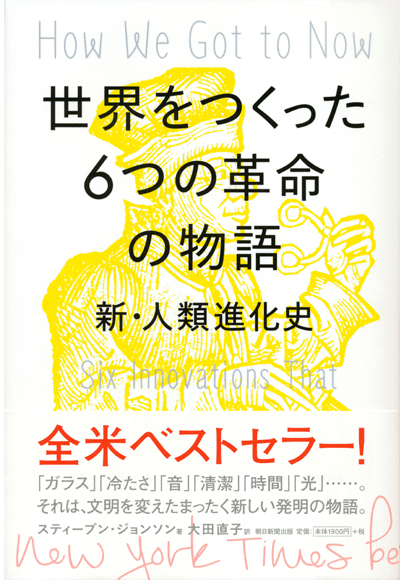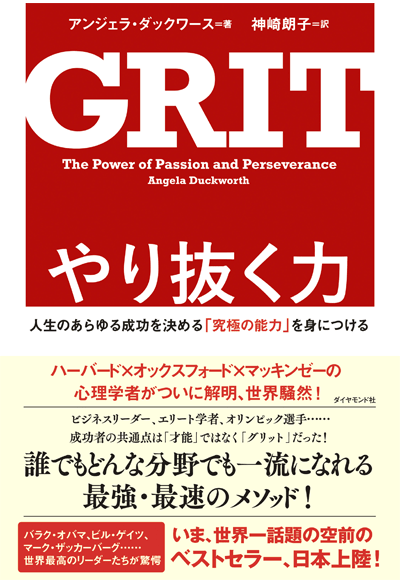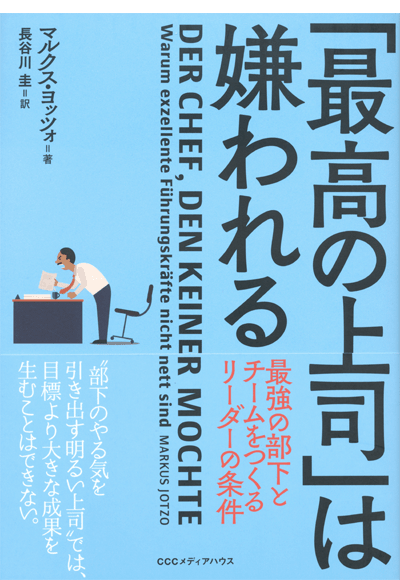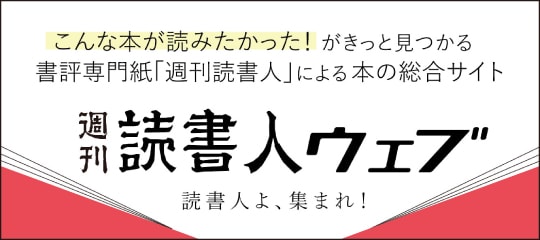2017年1月の『視野を広げる必読書』

業界のガリバーが仕掛けた個性的なビアレストラン
都内にある、近頃評判のビアレストランを訪れる機会があった。
その店のホールの中央には、スケルトン素材でできたビールの仕込み釜と発酵タンクが鎮座していた。なんと、レストラン内の施設で6種類のクラフトビールを醸造しているのだ。しかも客はガラス越しにビールが醸造されていく様を見ることができる。
メニューを眺めると、それぞれの種類のビールに合った多彩な料理が載っている。それを見て、海老のアヒージョと一緒に「白ワインのような味わいを楽しめる」との触れ込みのビールをいただくことにした。確かにソーヴィニヨン・ブラン(フランス西部を原産地とする白ワイン用ぶどう品種)を想起させる、おいしいビールである。
代官山にあるこのお店の名前は「スプリングバレーブルワリー」(以下、SVB)という。
このおしゃれで個性的な店は、実は老舗の国産ビール大手、キリンビールが手がけている。キリンビールといえば、「ラガー」や「一番搾り」など定番ブランドのビールを大量生産し、一般家庭や飲食店に提供しているイメージが強かった。なのにどうして、少量多品目のクラフトビールに目を向けたのだろうか。
その背景には、国内ビール市場の急激な市場縮小があると考えられる。かつては圧倒的なシェアを誇ったキリンビールだが、1987年のアサヒビール「スーパードライ」発売以降シェアを減らし、後にトップシェアを奪われたことはよく知られている。だが、その頃はビール市場全体のパイがまだ大きかったため、もちこたえられた。ところが、ビール全体の国内総出荷量は1994年をピークに減少しはじめる。それにともないキリンビールも業績の悪化に苦しむことになる。
SVBの立ち上げは、そんな状況を打開しようとビール市場全体の活性化も視野に入れた挑戦だった。しかし、その道のりは平坦ではなかった。それまでのビジネスモデルに半ば背を向けることになるため、キリンビール社内の多数が反対したからだ。
本書『究極にうまいクラフトビールをつくる』は、幾多の困難を乗り越え「ビールの未来」を拓こうとする、キリンビールの「異端児」たちの姿を描いたビジネス・ノンフィクションである。著者の永井隆氏は元「東京タイムズ」(1992年に廃刊)記者のフリージャーナリスト。『サントリー対キリン』『ビール15年戦争』(ともに日本経済新聞出版社)など、ビール業界に関する著作が多数ある。
消費者にビールの“本当の魅力”を知ってもらいたい
SVBのプロジェクトは2011年、マーケティング部内での有志が非公式に始めた。ゴーサインを得るまでの社内調整、醸造施設を併設できる広大な土地探し、クラフトビールづくりのノウハウ取得……。それだけではない。現在SVBの大きな特徴となっているスケルトンの釜は、銅やステンレスの釜を使用するビール醸造の常識からすると、ありえないとされるものだ。こうした数々の苦労を重ね、2015年1月に専門子会社設立、同年3月に「スプリングバレーブルワリー横浜」、4月に代官山の「スプリングバレーブルワリー東京」をオープンした。来店者数は目標を上回るペースで伸びているそうだ。
ビール産業は装置産業と言われることが多い。商品開発や工場に大規模な投資を行い、機械設備を駆使した大量生産により利益を得るというのが主流のビジネスモデルだ。その場合、生産品目を絞った方が利益が出やすい。キリンビールも一番搾りなどに集中して投資する戦略をとっていた。その対極である少量多品目生産が特徴のクラフトビールへの進出は、とくにキリンのような老舗の大企業の社内では異端の考え方だったに違いない。
その異端の考え方をどのように具現化していったのか。本書には、SVBのプロジェクトをリードした社員たちや経営者が、どのように考え行動したかが克明に描かれている。まずはプロジェクトを始めた二人の人物に着目してみよう。
一人は、現在SVBの社長を務める和田徹氏だ。マーケティング部に所属していた和田氏は「淡麗」や「氷結」といった人気商品を生み出したヒットメーカーでもある。ノンアルコールビールやギネスの黒ビールなどにも関わり、ビールの個性と奥深さを再確認したこともある。
こうした経験を経て和田氏は、改めて国内のビール市場の現状を眺めてみた。2011年当時は、大手四社(アサヒ、キリン、サントリー、サッポロ)がつくる定番のビールを、相変わらず皆が同じように「とりあえずビール」と言って飲んでいた。和田氏は、「ビールの本当の魅力を十分人々に伝えられていない」と、強い危機感を覚えるようになった。
そこで和田氏は、その頃アメリカで人気に火がついたクラフトビールに注目する。日本でもさまざまなタイプのクラフトビールが登場すれば、ビールの多彩な魅力がもっと伝わるのではないか。「ビール離れ」が指摘される若者たちにも「ビールってカッコイイ」と感じてもらえるにちがいない。そう信じた和田氏は、SVB実現への一歩を踏み出すことになる。
そんな和田氏のビジョンに共鳴したのが当時入社6年目だった吉野桜子氏。当時の磯崎功典社長にプレゼンテーションをする機会を得た和田氏は、吉野氏にスクリプト(台本)の作成を指示する。彼女はパワーポイント14枚からなる熱のこもった“宣言文”をつくり上げた。
プレゼン当日、和田氏の説明の後に吉野氏が思いを語った。「社会の価値観は大きく変わりました。そんな中、私たちキリンビールは、企業としての在り方や、ビールのつくり手としての在り方、そしてお客様との関係性を問われています。ビールそのものも、若年のビール離れ、市場の縮小という形で、存在意義が問われています」
ビールは本来、大麦や小麦などの農産物の加工品である。単なる大量生産の工業製品と片づけられない魅力があるはずだ。醸造の方法、加減によって味わいが大きく変わる。ワインや日本酒に負けないほど味にバリエーションをつけることも可能なのだ。そうしたことを踏まえ、吉野氏のプレゼンはこんなふうに締めくくられた。「もっとうまいビールを追求しつづけたい。それを味わえる喜びをお客様と分かち合いたい。多くの人たちにビールが生命(いのち)から出来ていて、もっと自由で楽しいお酒であることを知ってもらいたい。そういうシンプルなイメージを伝えていくこと。それがキリンとお客様との新しい関係の、そして『ビールの未来』の、スタートラインです」
二人の思いは伝わった。磯崎氏は社長としてこのプロジェクトにゴーサインを出す。しかしその後、キリンビールの業績はさらに悪化した。ビール市場全体が縮む中、キリンはさらに業界で“一人負け”に陥っていた。当時、市場の1%にも満たないクラフトビール(その頃は地ビールと呼ばれていた)で挽回できるのか、と社内の大半がプロジェクトに反対するようになる。記者発表後のマスコミの論調も同様だった。だが、それでも磯崎氏はSVBのプロジェクトを強く支持し続けた。
チャレンジのルーツにあった「異端の教え」
本書を読むと、和田氏や磯崎氏のチャレンジ精神の源流に、一人の人物の存在があることがわかる。その人物とは1980年代にキリンビールの専務取締役だった桑原通徳氏(故人)である。キリンビールが一人勝ちをしていた80年代前半に神戸支店長だった同氏は、既存の酒販店(いわゆる酒屋)に頼ったビジネスモデルは長くもたないことをすでに見抜いていた。いずれ酒販免許が自由化され、スーパーの店頭にビールが並ぶようになる、容器もリサイクルされるビンから使い捨ての缶が主流になる、酒販店による一般家庭への配達は廃れていく……、これらの桑原氏の“予言”は現実のものとなった。
専務になった桑原氏は「このままではアサヒに負けます」と、改革の必要性を経営陣に訴えた。役員室では失笑が漏れたという。社長候補に目されていた同氏はやがて子会社に転出となる。磯崎氏は神戸支店時代に、桑原氏の薫陶を受けている。また、桑原氏の直弟子と言われたのが一番搾りの開発リーダーだった前田仁氏である。前田氏は部下だった和田氏を引き上げ、淡麗の開発を任せた。こうして桑原氏の変革のDNAは受け継がれ、SVBに結実したのだ。
「変わることができなければ、強い組織にはなれない」「成功体験をすてろ! アンラーニング(いったん身につけた知識を忘れ、学び直すこと)せよ!」「学んできた知識、既存の価値観を超えて、新しいものをつくるんだ」「お前たちは好きなようにやれ。ただし、物事の本質を見ろ!」。桑原氏はこんな言葉で部下に発破をかけ続けたという。SVBの発想は、まさにこれらの教えを地でいくものといえる。大量生産のビールでの利益獲得という成功体験に背を向け、消費者にビールの魅力を感じてもらうという本質を突き詰めたのだから。(担当:情報工場 足達健)