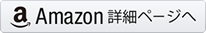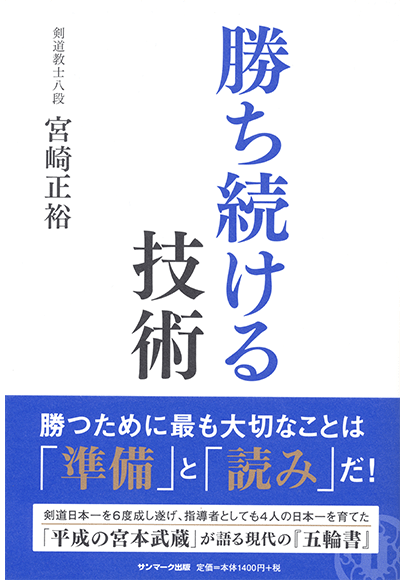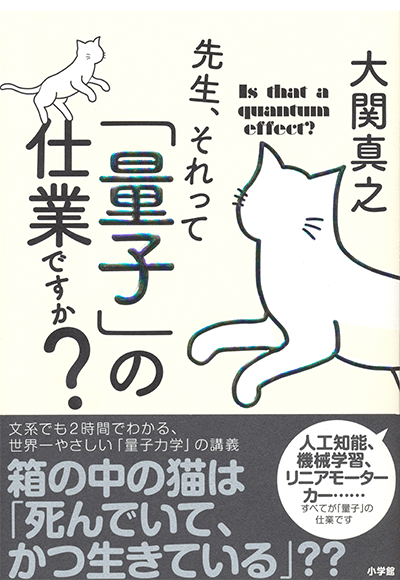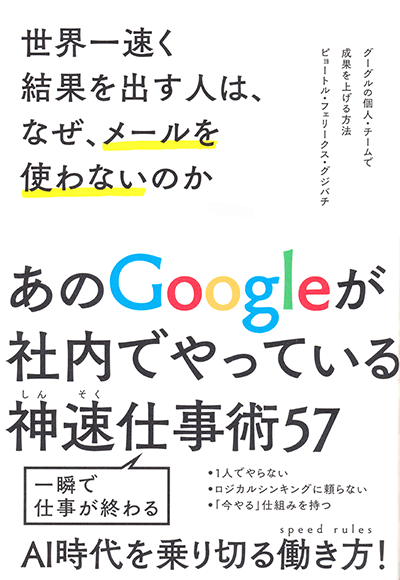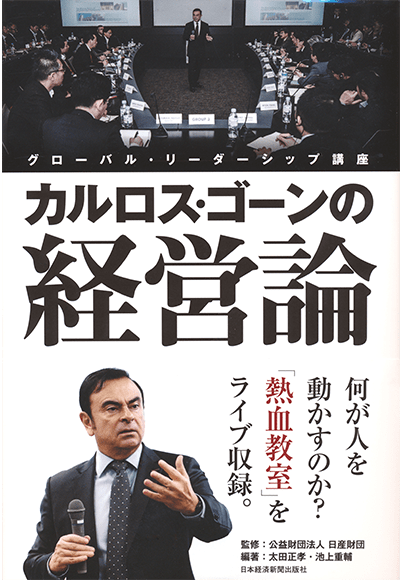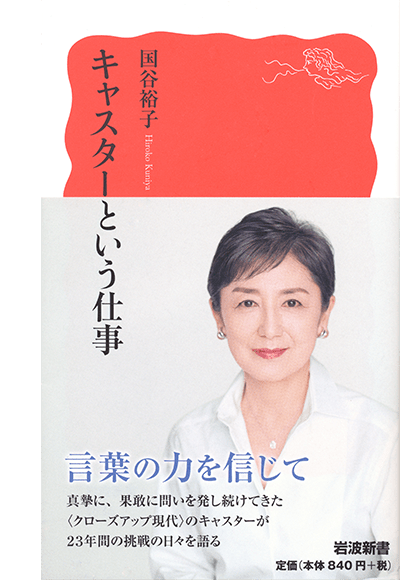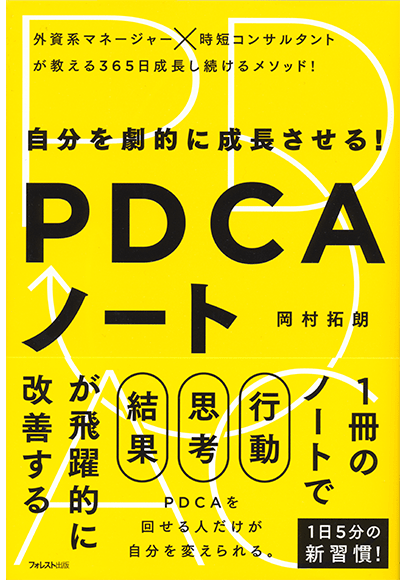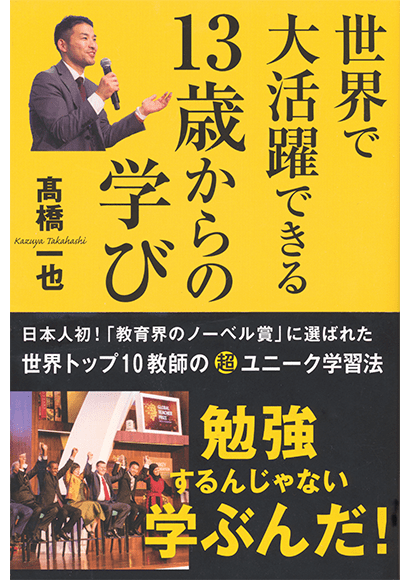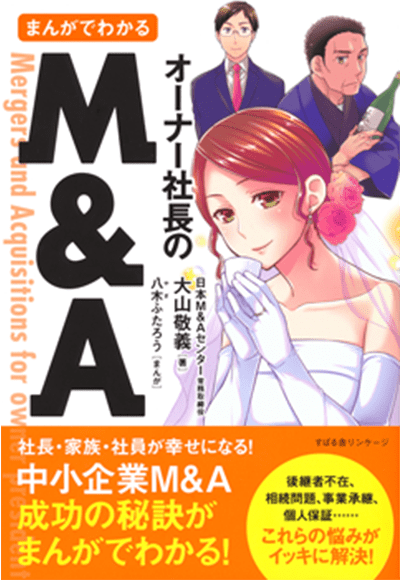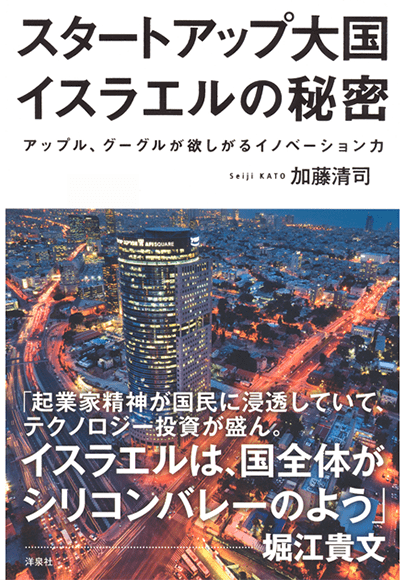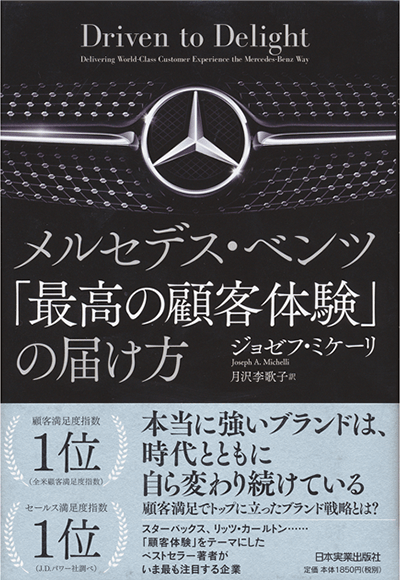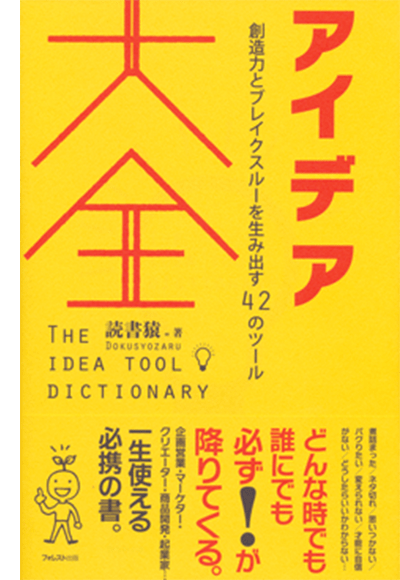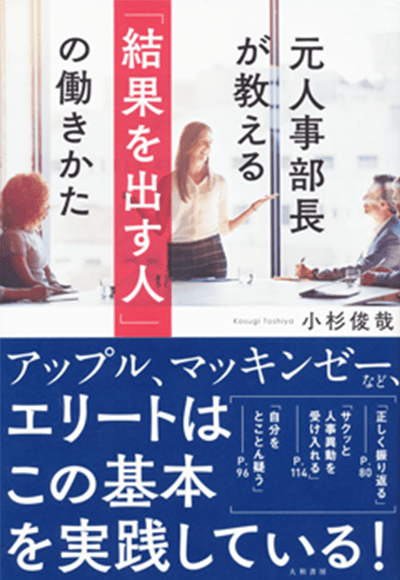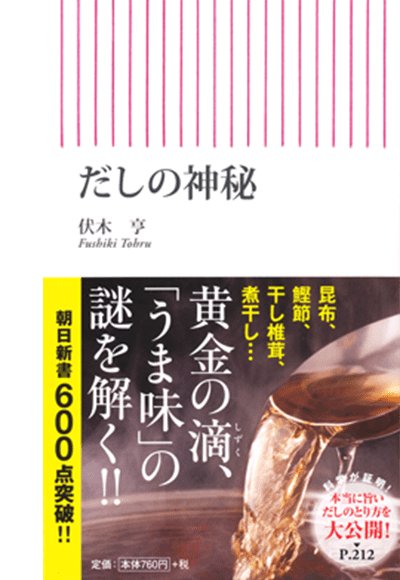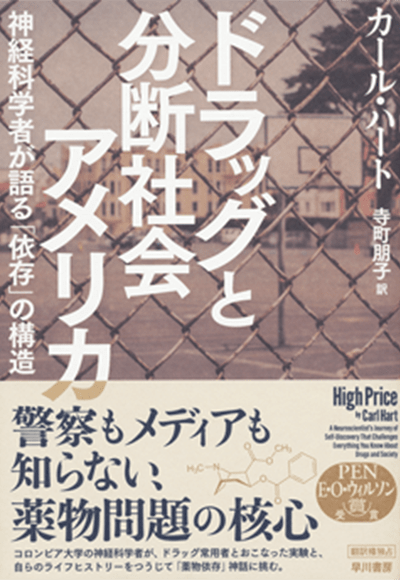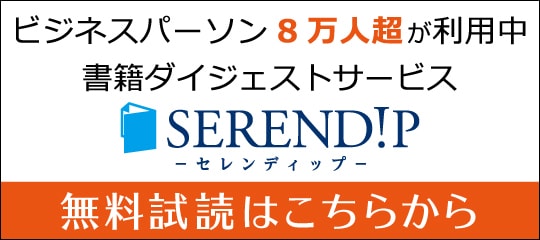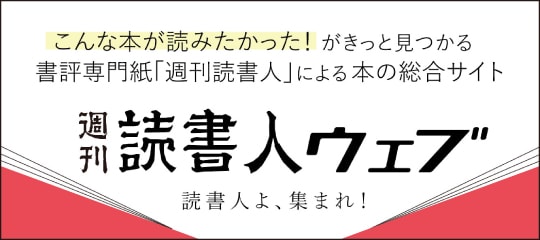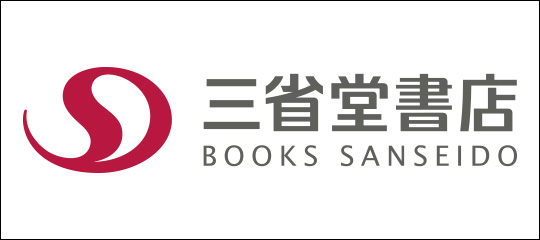2017年5月の『押さえておきたい良書』
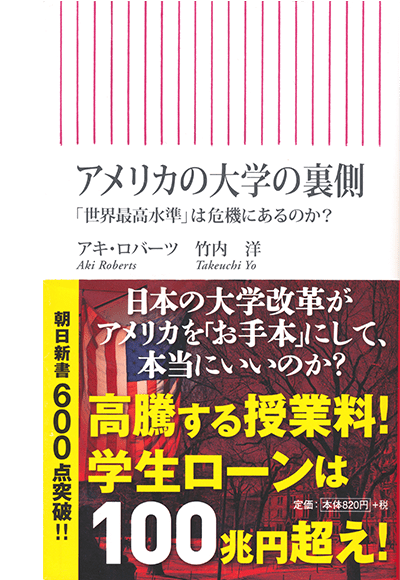
イギリスの教育専門誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」の世界大学ランキングの最新の順位(2016-17)が発表されている。その上位10校のうち、半数以上がアメリカの大学だ。論文の引用数など、研究面のレベルの高さを示す指標で見ても、同様に上位を占めている。他の調査機関のランキングでも似た結果が出ていることもあり、大学改革の際にアメリカをお手本にする他国の大学も多い。だが、実際のアメリカの大学は、必ずしも「お手本」になるものばかりではないそうだ。
本書『アメリカの大学の裏側』は、多くの問題を抱えるアメリカの大学の実情をリポートしている。著者の一人、アキ・ロバーツ氏はウィスコンシン大学ミルウォーキー校の准教授で犯罪学・統計社会学が専門。その父親で本書1章分を担当している竹内洋氏は教育社会学・歴史社会学が専門で、関西大学東京センター長を務めている。
本書によればアメリカの大学が抱える問題は、アメリカの社会問題とも関係がある。そして、日本の大学や社会にも、同様の問題が発生する可能性が高いという。
ミレニアルズと大学、負のエンドレス循環
本書では1980年代以降に生まれた、いわゆるミレニアルズの学生の問題を指摘している。彼らは親に甘やかされて育ってきたために、ぜいたくと快適さへの要求が強いといわれている。最近のアメリカの大学は、そんな世代の学生を獲得するために、教育よりも施設を豪華にすることに腐心する傾向があるという。
たとえば日本の大学で寮といえば、質素なイメージだろう。しかしオハイオ州立大学の学生寮は約37億円をかけて建設されており、フォー・シーズンズホテルと遜色ない豪華さだといわれている。他の大学もキャンパス内をリゾート地のように改装したり、入学時に携帯電話とパソコンを支給するなど、様々なぜいを凝らした環境を用意している。
しかし高級な施設を維持するためには、高額な学費が必要になる。結果、学生側は高い学費を払っているのだからとさらに良い施設を期待し、大学側はそれをかなえるために学費を上げる、というエンドレスな悪循環が発生しているのだ。
世界一高い授業料と学生ローン地獄
本書によれば、日本では四年制私立大学の年間授業料が平均86万円。対してアメリカは前述のような経緯もあり、300万円超にもなるという。そこでアメリカの大学生はファイナンシャル・エイドと呼ばれる、奨学金や学生ローンを利用するのが一般的だ。本書によればアメリカでは8割以上の学生が何らかのファイナンシャル・エイドを受けているという。
奨学金だけでは学費を賄いきれない場合は、学生ローンに頼ることになる。しかしアメリカの大学の奨学金の多くは返済不要だが、学生ローンは卒業後に多額の返済が待っている。返済に追われ、結婚や出産が困難になる人が増えているという話もあり、大学進学がむしろ貧富の格差を拡大しているような状況なのだ。
大学側も、3年で学士号が取れる短縮プログラムを導入するなどの対策を講じている。学費を1年分節約させるためだ。しかし現状、ローン地獄の解決にはつながっていない。(担当:情報工場 宮﨑雄)