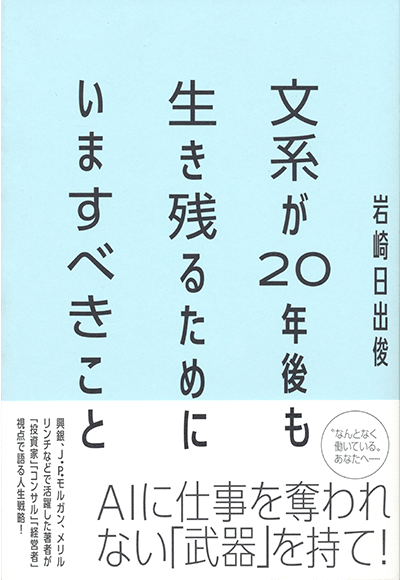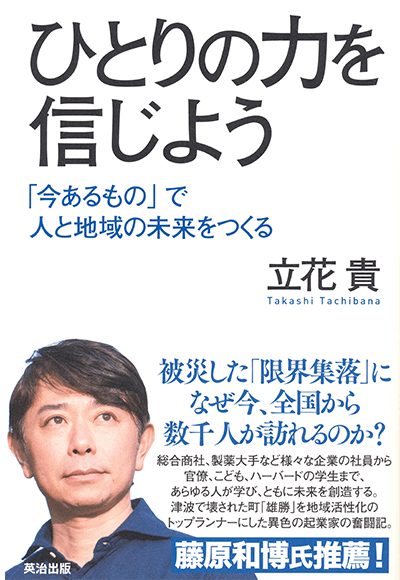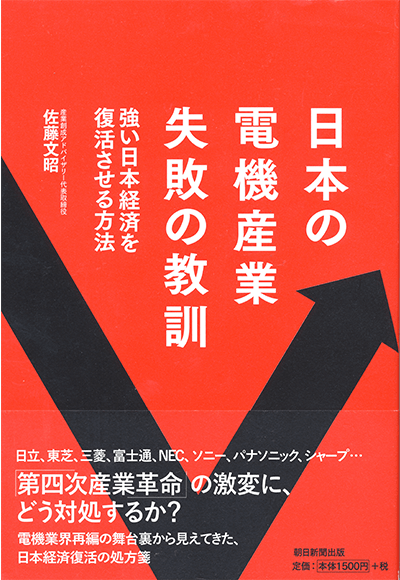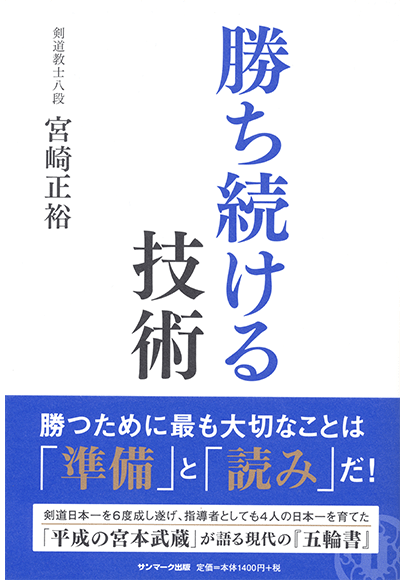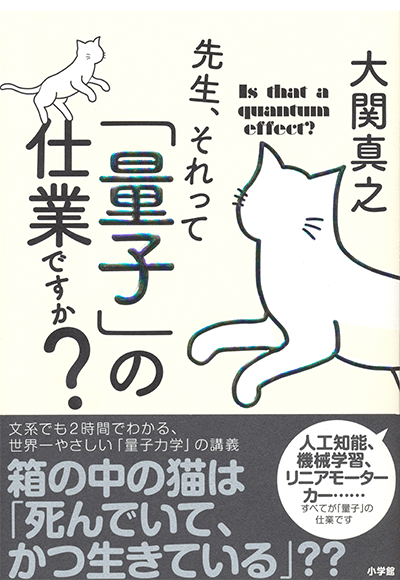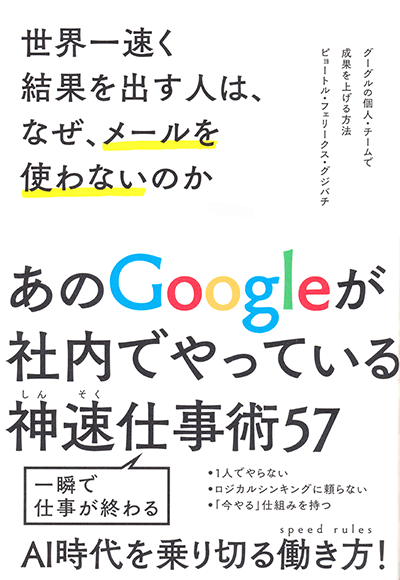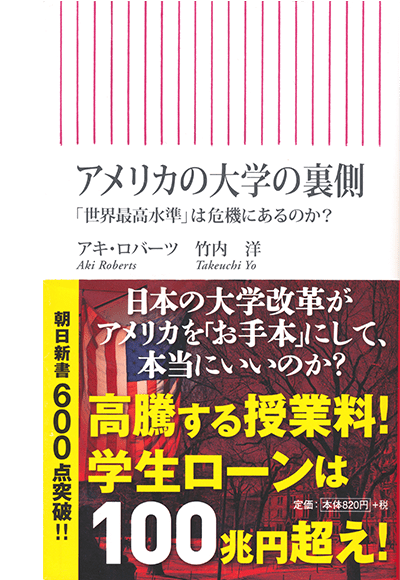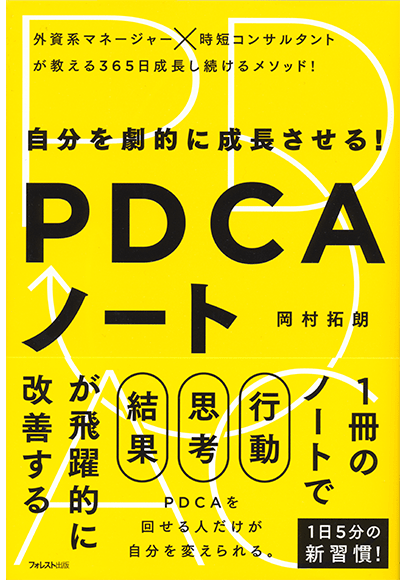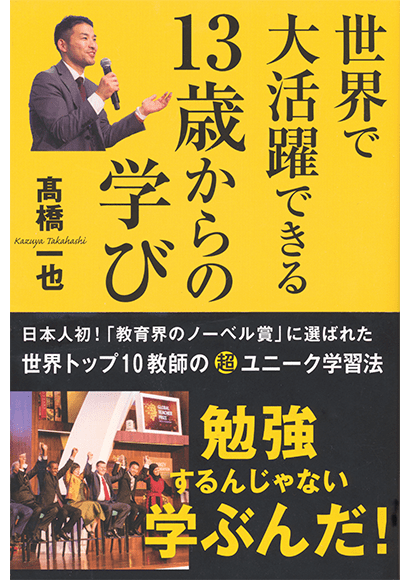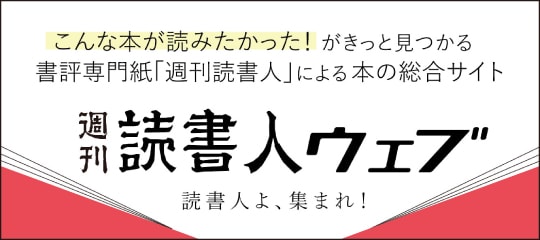2017年6月の『押さえておきたい良書』
「火」は、食材を焼く、鉄を精製する、発電など、多様な用途で使われ、人間にとってなくてはならないものだ。
人は古来、自分で薪などを用いて火をたき、生活してきた。だが現代の火は、ライターなどの機械やガス会社といったインフラを通じて社会から提供されるものになった。個人が火を自ら起こして利用する機会は少なくなっている。
だから、個々人の「火を使いこなしている」という感覚は以前より薄れているかもしれない。だがそれでも人類は、確実に火に依存して生きているのだ。
本書『火の科学』では、そんな火の果たしてきた役割を、さまざまな角度から考察している。人類が初めて使った火、家庭内で使われてきた火、宗教に登場する火、エネルギーとして活用される火などがテーマだ。自然環境に与える影響など、今後人類が火とどう関わっていくべきかについても、歴史学、環境科学などを踏まえて言及している。
著者は石川島播磨重工業(現・IHI)に勤務後、宇部工業高等専門学校物質工学科教授を経て、現在は帝京平成大学健康メディカル学部医療科学科教授。環境化学、環境プロセス工学を専門としている。
火の共同管理から社会行動が生まれる
火は、互いに協力し合う社会行動をする人類の特性を獲得するのに一役買ったようだ。著者の推察によれば、人類が初めて使用した火は「山火事の残り火」だった。そこから火を手に入れ、獲物を焼いて食べたり、害をなす獣を追い払ったりした。
当時の人類はまだ自分で火を起こせなかったので、手に入れた火が消えてしまうと、再び山火事が起こるのを待たなければならなかった。火は非常に貴重なものであり、集団でしっかり管理する必要があったのだ。
火を共同管理しようとすることで、火の番をする、燃料となる木を集める、食料を採集する、といった役割分担が生じた。そうして現代にもつながる社会行動の原型が作られていった。
生活の中心である竃(かまど)への信仰
また、人類は火に人知を超えるものを感じとり、信仰の対象にしてきた。灯籠(とうろう)流しや京都五山の送り火といった日本の伝統行事も、火への信仰の一種といえる。同じような火にまつわる行事や風習は、世界各地に存在するそうだ。
本書では、日本古来の、火が土着宗教と結びついた例として「竈(かまど)への信仰」を紹介している。どの家庭にもあった、調理などのために火を起こす竈には、火の神である「竈神」が住むと考えられていた。
上記引用と同様の習慣は、ギリシャやドイツなどにもあるそうだ。著者は、火が人類にとって「日常性そのものの象徴」だったのではないかと指摘する。日常性は家庭生活に宿るものだ。日々の食事を供給する竈は、その家庭生活の中心的存在と言っていいだろう。だからこそ竃の火に対する感謝と畏れの気持ちは、洋の東西を問わず共通しているというのが、著者の見方なのだ。(担当:情報工場 宮﨑雄)