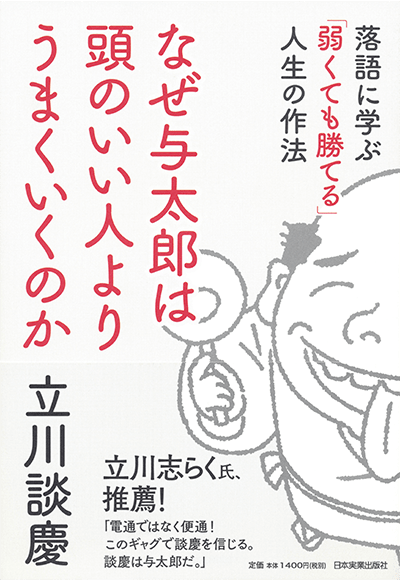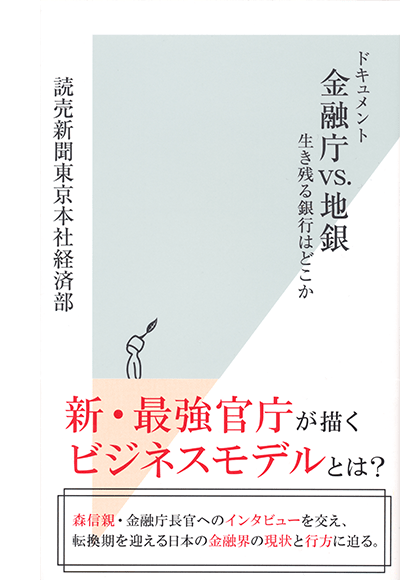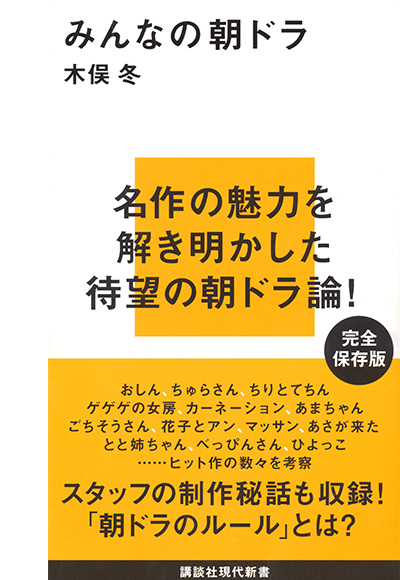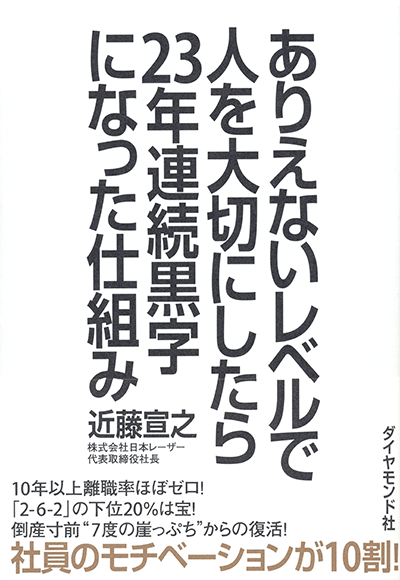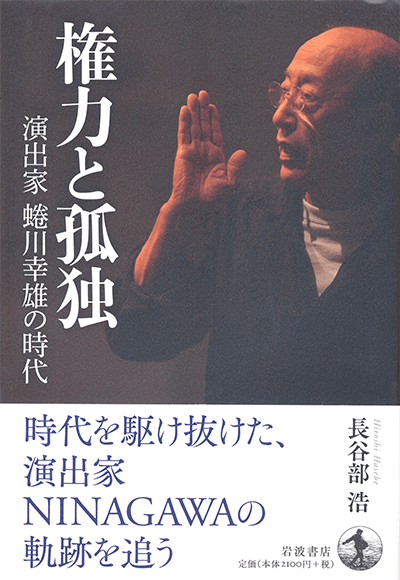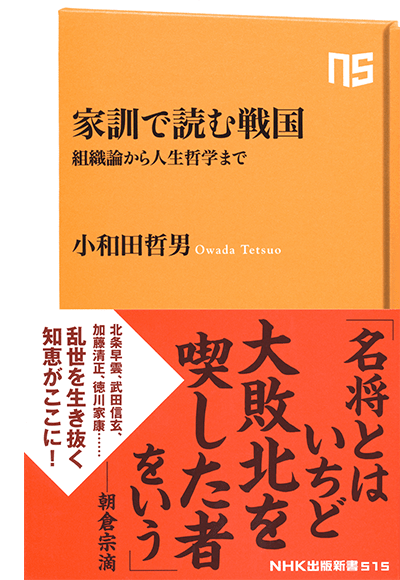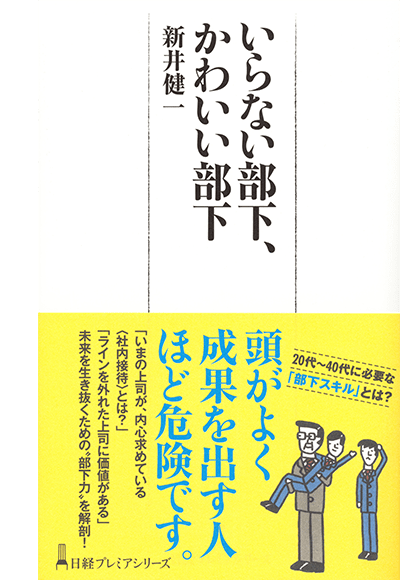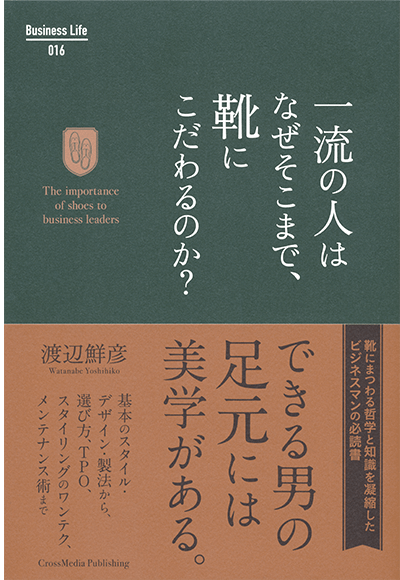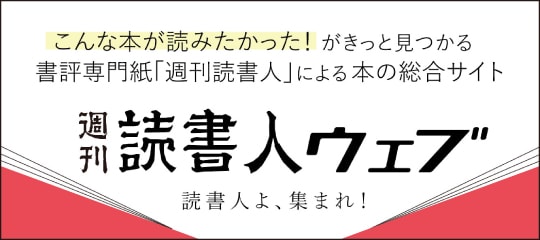今月の『視野を広げる必読書』
「イノベーション=技術革新」ではない
イノベーションという言葉は、日本では「技術革新」を意味することが多い。これは、1958年に当時の経済企画庁が作成した『経済白書』(現在は内閣府が作成)でイノベーションを技術革新と訳したことに端を発しているそうだ。
しかし、「イノベーションの父」とも呼ばれるヨーゼフ・シュンペーターは、イノベーションを「経済活動の中で生産手段や資源、労働力などをそれまでとは異なる仕方で新結合すること」と定義している。新結合とは、新しい組み合わせを考えることを意味する。
たとえば、民泊サービスのエアビーアンドビー(Airbnb)は、「空き部屋を貸したい個人」と「宿泊をしたい個人」という新しい組み合わせによる、イノベーティブなサービスを提供している。このサービスに技術革新の要素はほぼ皆無だ。
つまり、イノベーションに技術革新は必須ではない。むしろ新結合を考案し、そのために、ルールやプロセス、組織を革新していくことこそが、イノベーションの本質なのだ。
本書『イノベーターたちの日本史』は、明治維新前後から昭和初期にかけての近代日本において、さまざまな領域でのイノベーションがどのように起こったのかを解き明かしている。
著者の米倉誠一郎氏は、一橋大学イノベーション研究センター特任教授、法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授。主な著作に『経営革命の構造』(岩波新書)、『創発的破壊――未来をつくるイノベーション』(ミシマ社)などがある。企業のイノベーションを核とした経営戦略と発展プロセス、組織の史的研究を専門とする研究者だ。
明治維新といえば、倒幕運動の指導者として活躍し、江戸城の無血開城に関わった西郷隆盛や、維新政府体制の青写真を描き大政奉還の成立に尽力した坂本龍馬といった幕末の志士たちの名前がすぐに思い浮かぶだろう。
しかし彼らは、表舞台で明治維新の方向づけをしたにすぎない。その裏側で、あるいはそれを受けて、日本の国体と、当時の西洋世界のスタンダードだった中央集権型の近代国家との新結合を実現する壮大なイノベーションを行った者たちが存在した。
本書では、これまで取り上げられることが少なかった彼らこそ「イノベーター」であるとし、光を当てている。そして彼らが、それまでとはまったく異なるさまざまなルールやプロセス、組織をどのように創造・改革してきたかをダイナミックに描いている。
高島秋帆の高い「情報感受性」が黒船来航から日本を守る
現代の世界では、グローバリゼーションが急速に進展するとともに、その反動ともいえる孤立主義(自国中心主義)の台頭が見られる。米倉氏は、こうした状況が、幕末の西欧諸国によるアジア諸国の植民地化の動きや、日本国内での攘夷(じょうい)運動をほうふつとさせると指摘する。
19世紀中ごろの清朝中国は、広州に限り、特許を与えた欧州商人のみと貿易を行うという、日本の鎖国に近い政策をとっていた。1840年に英国はその政策の放棄を迫り宣戦布告、アヘン戦争(1840~1842年)が勃発した。敗れた清朝は多額の賠償金を支払うとともに、香港の割譲、広州、厦門、福州、寧波、上海の開港を余儀なくされた。
それから約10年後、日本は浦賀に黒船で来航した米国のペリーに開国通商を迫られることになる。その時に対応策をまとめたのが高島秋帆(しゅうはん)という人物だ。
砲術家だった秋帆は、日本と西洋の砲術にあった格差を熟知していた。さらに、アヘン戦争の一部始終や、当時の中国の状況もよく理解していた。中国やオランダ、朝鮮半島など複数のルートで情報収集をしていたからだ。
秋帆には、自らが持つ情報を総合すると、日本がペリーの要求を拒み開戦しても勝ち目はなく、中国と同様な目にあうだけだ、ということが見えていた。
そこで秋帆は、「日本のような小国が生き残る道は通商和平であり、海外の良いものを積極的に取り入れて学ぶ以外にない」と主張する。そして当時としてはきわめて進歩的な、開国通商を受け入れる方策を提案したのだ。
そのすぐ後に、幕府は開国を決意する。それまでごく限られた国としか交易していなかった日本が、一転して世界各国との通商を受け入れるという大きなイノベーションに踏み切ったのだ。米倉氏は、この幕府の判断に、秋帆の提案が影響したのではないかと推測している。
米倉氏は、世界情勢に対する秋帆の「情報感受性」の高さを評価している。そして、世界情勢の正確な知識をベースにした的確な判断によるイノベーティブな構想が、明治維新でのさまざまなイノベーションのベースになったと分析する。
ベンチャーファンドと同様の施策を行った大隈重信と理研
ところで、明治政府が、今のベンチャーファンドにも似た政策を実行していたと聞いたら驚くだろうか?
明治政府は、士族に支給されていた俸禄(ほうろく)を廃止する際に、数年分の俸禄を合算した総額に利子をつけた金禄公債を旧士族に支給した。さらに、俸禄廃止で生じた余剰金を元手に、旧士族への起業資金の貸し付けを開始。並行して、職を失った旧士族を新たな産業の担い手に転身させる「士族授産」政策を実施した。この政策を推進した1人が、早稲田大学の創立者としても有名な大隈重信だ。
この制度の利用者には、たとえば小野田セメント製造株式会社創業者の笠井順八がいる。当時海外からの高額輸入品だったセメントの国産化を手がけ、国内における新産業創出に貢献した人物だ。
また、大正初期に設立され、数多くの科学者を輩出した理化学研究所(理研)も、ベンチャーファンドに近い機能を持っていたようだ。三代目所長の大河内正敏が導入したきわめて先進的で分権的な「研究員制度」により運営され、研究員に潤沢な資金を与えて自由に研究をさせていたのだ。
さらに理研は、研究成果をビジネスに変え、次の研究につぎ込む資金をしっかりと稼ぐというプロセスも確立していた。「ビタミンA」「感光紙」などの研究成果を自前で製品化し、それらの製品を取り扱う会社を傘下に設立していったのである。
士族授産制度や理研の取り組みがきっかけになり、日本は海外から多くの技術を取り入れ、国内でさらに発展させる技術革新を進めていくことになる。すなわち、今日までの日本の技術革新は、近代におけるプロセスイノベーションや組織イノベーションによってもたらされたといえよう。
現在の日本に目を移すと、かつては高い技術力を誇ったメーカーなどの大企業は軒並み停滞している。かつては有効だった組織体制や、技術革新プロセスが、もはや限界を迎えているのは明らかだろう。
中国の華為技術(ファーウェイ)が年内にも日本国内にR&D施設を新設する予定であることが判明している。また、米国のアマゾン・ドット・コムが豊洲に巨大な物流拠点を構築しようとしているという噂もある。さまざまな“黒船来襲”の知らせが毎日のように聞こえてくる。
今こそ近代と同様の危機感を持ち、根本的なプロセスイノベーションや組織イノベーションを検討する必要があるのではないだろうか。(担当:情報工場 浅羽登志也)