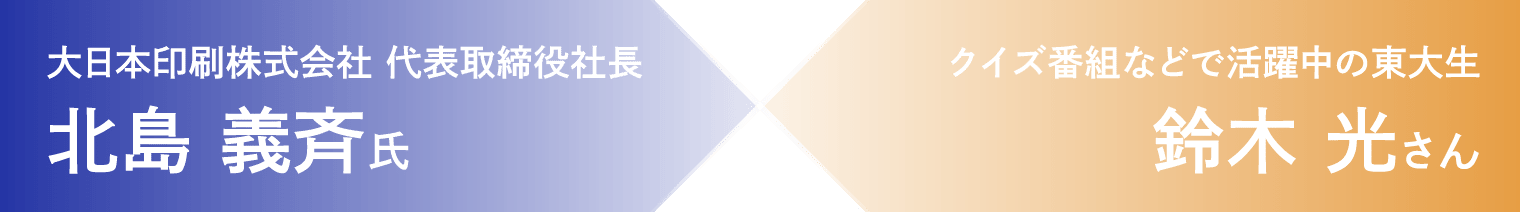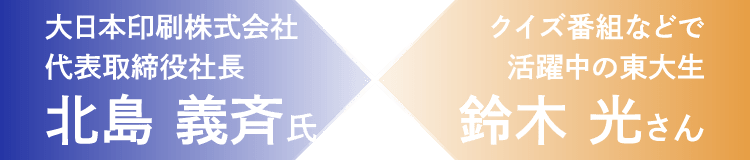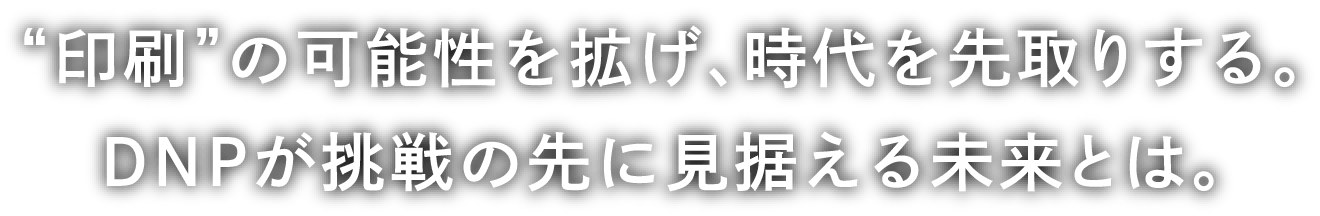コロナ禍の前から掲げる
「未来のあたりまえをつくる。」


───コロナ禍で世の中が一気に変わってきていますが、お二人にはどんな変化がありましたか。
鈴木大学が全部リモート授業になりました。通学があたりまえだったのに、1年近くキャンパスに行きませんでした。生活の中心が学校から家に変わりましたね。
北島我々の働き方も大きく変わりました。以前からテレワークの導入は進めていましたが、コロナ禍で一気に加速しましたね。事業活動の面では、コロナ禍で求められる遠隔や非接触、抗菌・抗ウイルスといったテーマの製品・サービス開発にも注力しています。鈴木さんのお話しに関連する教育ICTもその一つで、DNPはアナログとデジタルを掛け合わせ、学校でも自宅でも児童や生徒一人一人の学力に合わせた教材が使えるシステムを提供しています。
鈴木生活していると、どうしても外に行く必要がありますよね。例えば、病院です。そういうとき、接触を前提にしたものがあると実感します。券売機などもそうです。触れないと操作できないし、必要な情報を入力しないといけない……。そのような公共の施設などに、DNPさんの非接触型パネルがあればいいのに、とよく思います。
北島よくご存じですね(笑)。既存の端末や入力機にも後から設置するだけで、タッチレスパネルとして活用できるホログラム技術のことですね。ほかにも、接触せざるを得ない手すりなどの建装材や食品・生活用品などのパッケージの分野で、抗菌・抗ウイルス性能を持たせた製品なども開発・提供しています。
鈴木スマートフォンなどもその都度消毒する必要がなくなったら便利ですよね。普及が今から楽しみです。
───DNPは「未来のあたりまえをつくる。」というブランドステートメントを掲げていますが、どんな意味が込められているのでしょうか。
北島我々は、生活する人の身近に常にあって、「あたりまえ」に使えるものを開発したいと考えています。コロナ禍で「ニューノーマル(新常態)の構築」への対応が求められていますが、我々が考える「未来のあたりまえ」はどんな時代にも左右されない価値であり、その創出をめざしていますので、コロナ禍でもその本質が変わることはありません。
鈴木「未来のあたりまえ」って、きっと誰にもわからないことですよね。スマートフォンがこんなに浸透しているなんて、10年前に予想できた人は少なかったはず。だからこそ、このフレーズは、実はすごく挑戦的な言葉ですよね。同時に、新しい価値をつくり出そうとする姿勢が素晴らしいと思います。