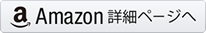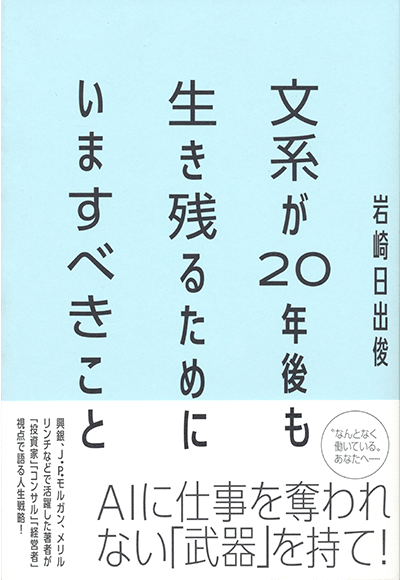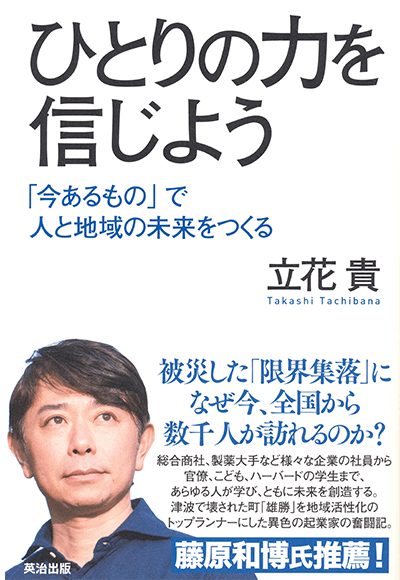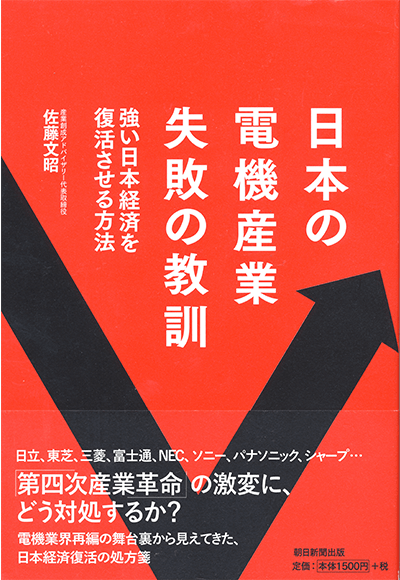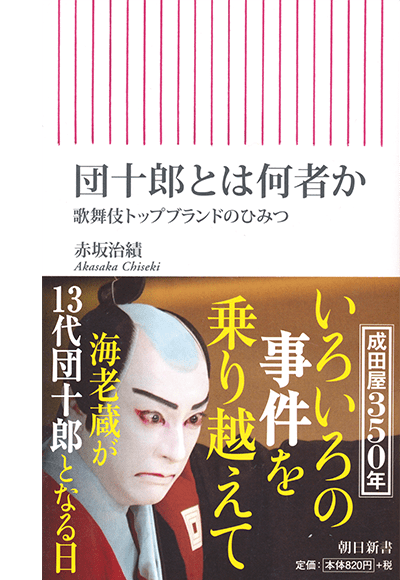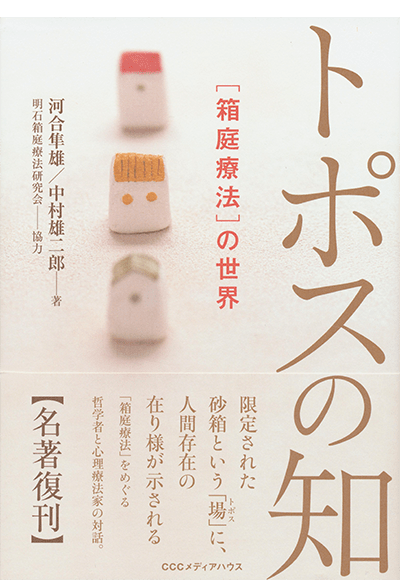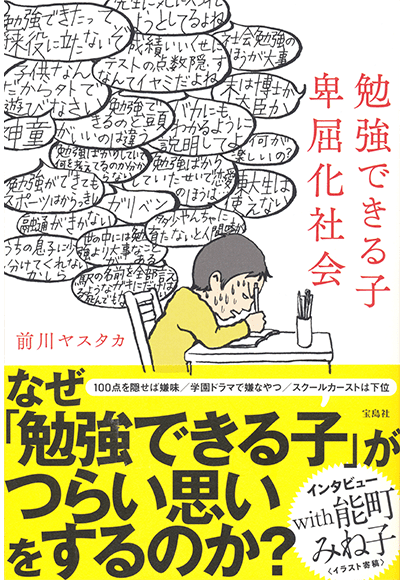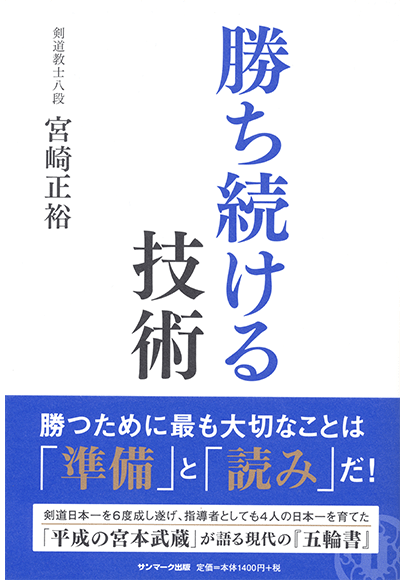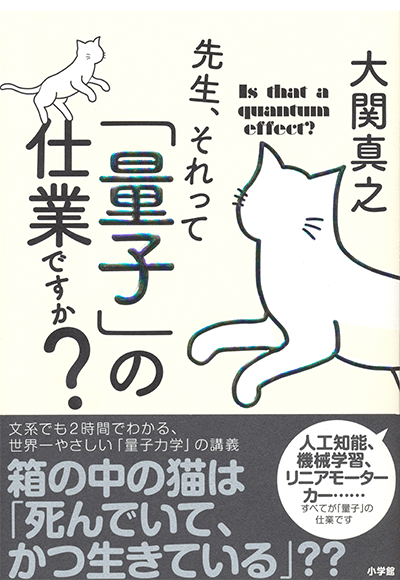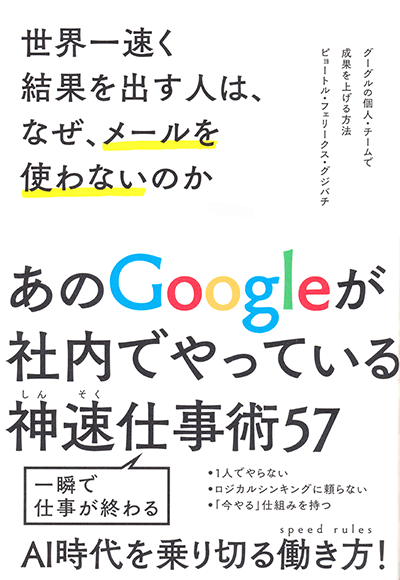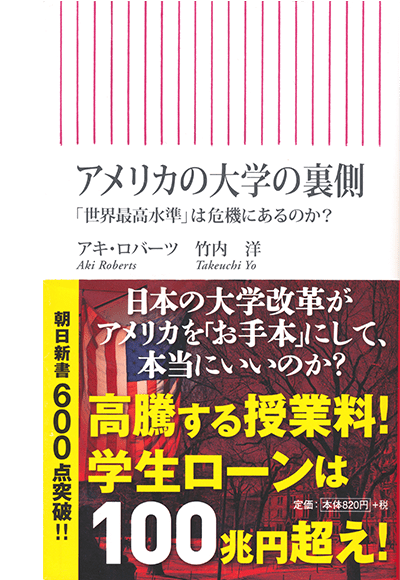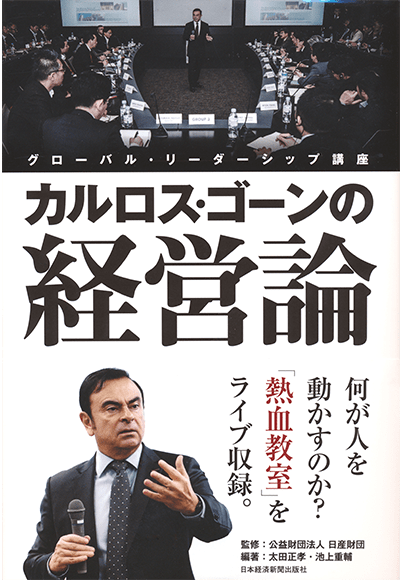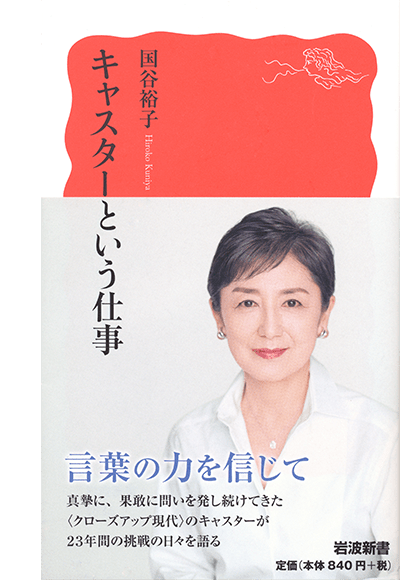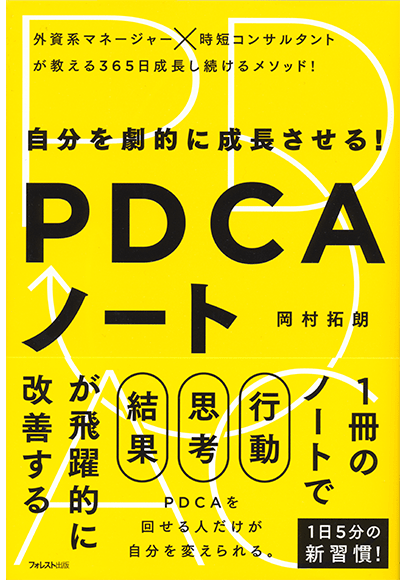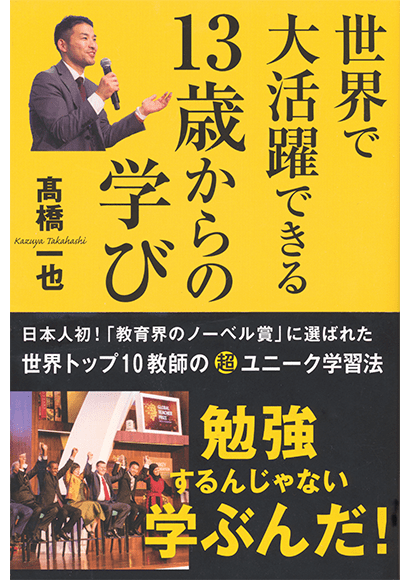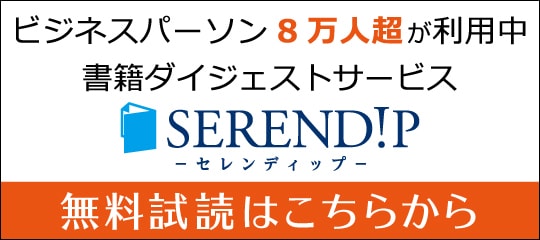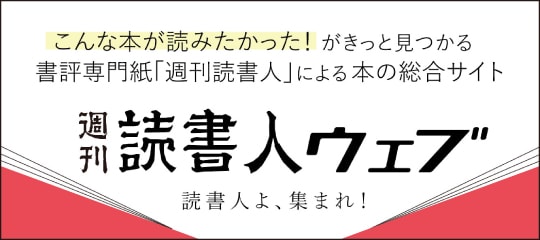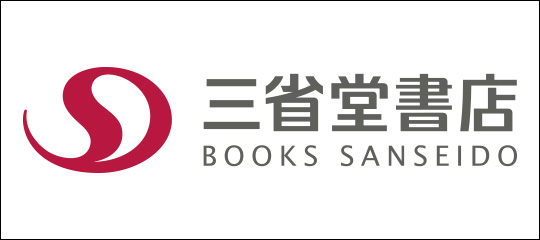2017年6月の『押さえておきたい良書』
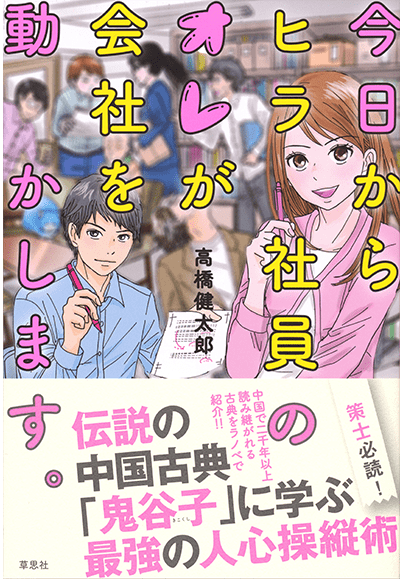
「諸子百家」と呼ばれる中国の思想家たちが残した古典の数々には、現代ビジネスに応用できる知恵がふんだんに含まれている。『孫子』の兵法、『韓非子』の法家思想などがよく知られるが、『鬼谷子(きこくし)』という書をご存じだろうか。作者は戦国時代(紀元前400年ごろ)に活躍したとされる鬼谷子。当時の遊説家、蘇秦(そしん)や張儀(ちょうぎ)に教えを授けたとされる伝説の人物だ。遊説の際の弁論と説得の法を述べた鬼谷子からは、現代企業の社内外における人心掌握術や交渉術を学べる。
本書『今日からヒラ社員のオレが会社を動かします。』では、ライトノベル形式でビジネス・ストーリーを楽しみながら鬼谷子のエッセンスを学べる。舞台は出版社。正反対の文化と経営方針を持つ二つの会社が合併したために、良い企画が通らなくなった編集部員の主人公が、社内のキーパーソンたちに働きかけ、策を練りながら健全な方向に会社を動かしていく。
著者は、古典や名著を題材とした作品を多数発表する作家。近年はとくに弁論術・レトリックをテーマに執筆活動を続けている。
『鬼谷子』の教えで合併企業のギクシャクを解く
主人公のチョウギ(あだ名)こと張本儀一は、出版社・共和帝国出版の若手ヒラ社員で、編集を担当している。共和帝国出版は、老舗の共和書房が、新興の帝国パブリッシャーズに吸収合併されて誕生した。前者は小規模だが読書好きから評価が高い良心的な出版社、後者は逆にヒット作を模倣した安易な企画で本を売りまくる売れ線狙いの出版社だ。チョウギは共和書房の出身である。
自分の企画がまったく通らず、ギクシャクした会社の空気に「何とかしなくては」と悩むチョウギは、ひょんなきっかけから、謎の老人と出会う。その老人はチョウギに、伝説の古典鬼谷子に著された人心掌握の奥義を授けるのだった。
自分を陰に、相手を陽におくのが大原則
「はあ」
「今でも占いの分野じゃ、この考えは生きておるがの。『鬼谷子』の術は、この陰陽に基づいて言葉を支配する術なんじゃ」”(『今日からヒラ社員のオレが会社を動かします。』p.33-34より)
上記引用のように、謎の老人は鬼谷子の教えの土台には陰陽思想があると説く。「陰あれば陽あり」と、物事には必ず陰陽の両面があるというのが陰陽思想の基本だ。
そして大事な原則として「常に自分を陰におくこと」を肝に銘ずるよう伝える。人を動かそうとする時には、こちらの狙いやたくらみを相手や周囲に気づかれないようにするということだ。
それと同時に、相手、すなわち動かす対象となる人は陽におく。相手の実情、目的、内心を明らかにしてしっかり把握する。こちらは相手のすべてを知っているが、相手はこちらの考えをまったく知らない、という状態をつくるのが鬼谷子の教えの大前提なのだ。
老人の教えを請いながら、上司や、社長の息子である後輩社員、他部署の社員を巧みに動かし目的を達成していくチョウギ。その痛快な活躍からは、さまざまな交渉ごとや、ちょっとした頼みごとなど、人に動いてもらいたい時の話し方、動き方のヒントが得られるだろう。(担当:情報工場 吉川清史)